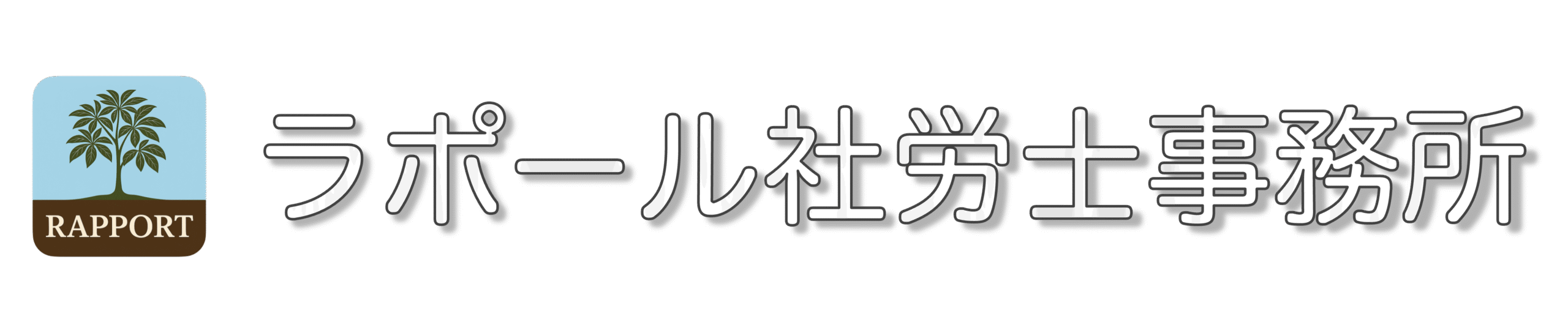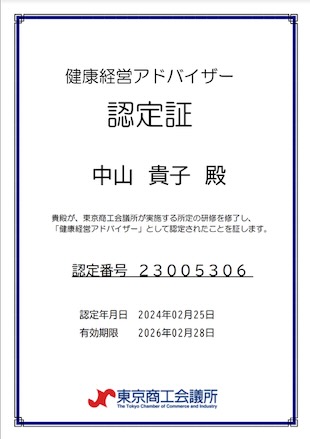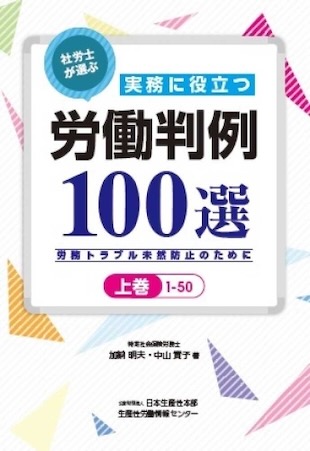1 報告の経緯
令和7年9月24日、東かがわ市議会ハラスメント調査特別委員会が、「市議会議長の職員に対するパワハラ行為」に関し、調査報告書を発表しました。これは、市長から市議会に対し、市議会議長の職員に対する言動について調査と厳正な対処を求める申し入れをしたことに端を発するものです。
問題とされた言動は、概ね以下のとおりです。
(1)「議長が市民との会合中の職員を呼び出し、見積書の提示を求めた」
(2)「市民との会合中の職員を別の事業に関することで呼び出した」
(3)「職員に対する呼びつけや厳しい口調での詰問が繰り返された」
(4)「市民がいる前での議長の発言により職員が強いストレスを感じている」
(5)「説明を何度も繰り返し求めたり、指摘を繰り返す」
(6)「市の業務範囲を超える要求」
(7)「市長と議長の2人で話している中で、議長が職員の進退に関する発言をしてきたという内容を記者会見で明らかにした」
2 市議会議長のハラスメント言動の評価方法
この報告書は、市議会議長の職員に対する言動について、「東かがわ市職員カスタマーハラスメントに対する基本方針」に基づき、カスタマーハラスメントの定義とされる3要件に該当するかを評価しています。市議会議長と職員との間には、雇用関係等の契約関係はないことから、その関係上発生したハラスメントはカスタマーハラスメントに準ずるものとして取り扱われたことが特徴的な点です。
3要件は、次のとおりです。
①クレーム・言動の要求の妥当性を欠くもの
②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
③当該手段・態様により職員の就業環境や業務遂行を阻害しもしくは職員の尊厳を傷つけるもの
そして、3要件全てを満たすものを「厳格評価(3要件すべて該当)」としてハラスメントにあたる行為と位置づけ、ただし多くの場で「1つでも該当すればハラスメントになりうる」と扱うケースも多いことから、その場合は「柔軟評価(1要件でも対象となれば該当)」として取り扱うこととしています。
3 第三者委員会報告書や判決文との違い
当該報告書は、事実認定の可否およびカスハラ3要件該当性について、職員からのヒアリング結果等を踏まえ、8名の委員の意見を総合的に評価しています。
弁護士等で構成される第三者委員会報告書や裁判の判決文では、「事実認定」「評価」をはっきりと記載しますが、この報告書は、委員それぞれが評価した内容を具体的に記載し、厳格評価・柔軟評価という形式で評価を行っており、裁判の手法とは違った体裁をとっているところが注目されます。
source:リーガルコネクション