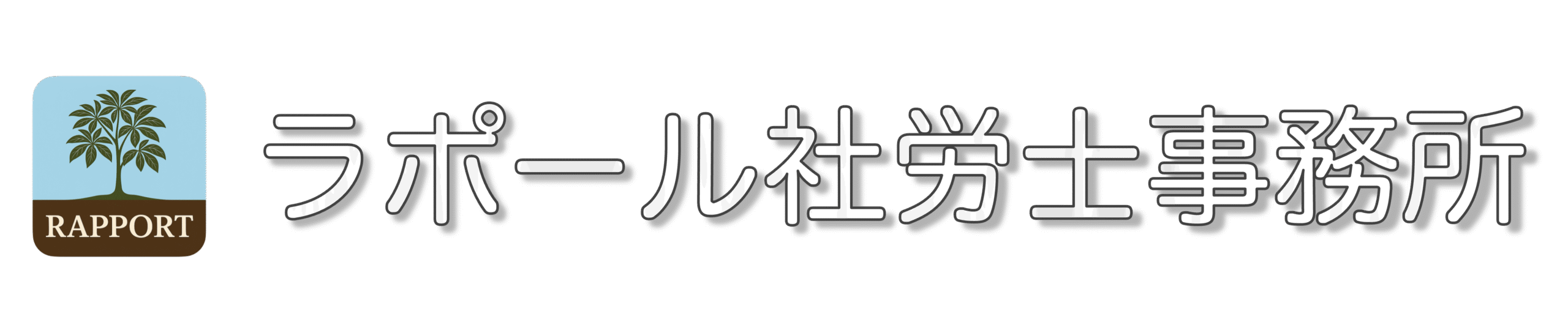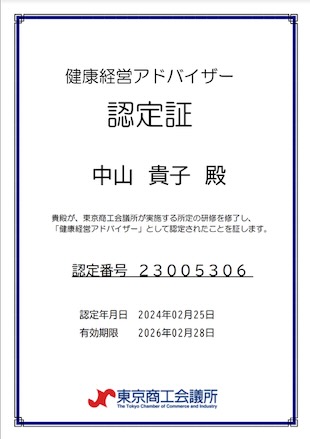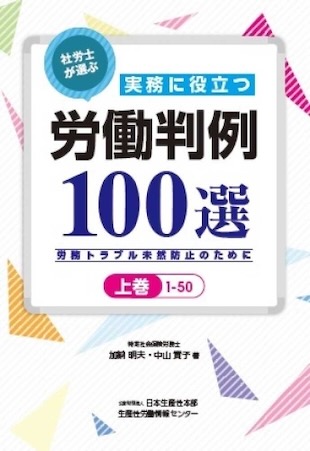1 自爆営業
厚生労働省は、「自爆営業」をパワハラ指針に明記する方針を示しました(詳細は、令和6年11月26日公開の「ハラスメントのニュースから⑦~自爆営業をパワハラ指針に明記へ~」をご参照ください)。これに先立ち、令和7年3月には「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点(いわゆる自爆営業を含む)」と題するリーフレットを厚生労働省が公表しました(厚生労働省のホームページ)。
2 民法や労働関係法令上様々な問題がある
当該リーフレットでは、商品の買取り強要等は、民法や労働関係法令上様々な問題があると指摘しています。そして、問題となる事例としてケースが4つ挙げられています。
(Case1)商品の購入強制
ケース1は、ノルマ未達の場合に、就業規則や口頭等で自社商品を購入するように求めた場合を想定しています。これは民法90条(公序良俗)違反の合意で無効となり、民法709条に基づき損害賠償の対象となることが指摘されています。また、商品代金の賃金控除をしている場合には、労基法24条(賃金の全額払)違反となることも指摘されています。
(Case2)懲戒処分や解雇
ケース2は、自社商品の購入を断った従業員を懲戒処分したり、解雇したりしたケースです。これは、労働契約法15条(懲戒権の濫用)、16条(解雇権の濫用)として、無効となると指摘されています。
(Case3)ノルマ未達の場合の人事上の不利益を懸念して自社商品を購入
ケース3は、ノルマ未達の場合に人事上の不利益取扱いを受けることを明示していたところ、労働者の判断で、自社商品を購入したケースです。これも、ケース1同様、公序良俗(民法90条)違反で買取契約が無効となり、民法709条の損害賠償の問題となることが指摘されています。また、人事上の不利益が懲戒処分である場合には、ケース2同様、労働契約法15条により、懲戒権の濫用として懲戒処分が無効となる可能性が指摘されています。
(Case4)現実的に達成不可能なノルマ
ケース4は、達成困難なノルマを設定し、ノルマ未達の場合は人事上の不利益処分をすることとしているケースです。
達成困難なノルマを設定することは、業務命令権の濫用として無効(労働契約法第3条第5項)となる可能性、また、不利益処分も無効となる旨が指摘されています。また、損害賠償(民法709条)の問題となることも指摘されています。
3 自爆営業がパワハラ指針に正式に追記される以前であっても、実現不可能なノルマの設定や、自社製品・サービスの購入を事実上強要するような慣行については、法的リスクが高いことに鑑み、会社として積極的に防止措置を講じる必要があります。
(source:新日本法規出版)
■参考となる裁判例(厚労省パンフより)
①いわゆる「商品の買取り強要」 ※Case1に関連した裁判例
~自社商品約18万円の購入を強要された事案~
〈事案の概要〉
数回にわたって会社から、「商品を理解しなければ仕事はできない、そのためには商
品を買う必要がある」と強く言われていたが、購入を拒否していたところ、重ねて「商
品を理解しない者には仕事をさせるわけにはいかない」と言われたため、やむを得ず
自社商品を購入した営業職の事案。
〈裁判所の判断〉
使用者としての立場を利用して、仕事をさせることにからめて従業員に不要な商品を
購入させたものであるから、公序良俗に違反する商法であり、不法行為を構成するも
のと判断。商品代金相当額の損害賠償請求が認容された。
(東京地裁 平成20年11月11日判決)
②合理的な理由のないノルマの設定 ※Case4に関連した裁判例
~1日100件の新規顧客開拓業務を指示された事案~
〈事案の概要〉
専ら飛び込みでの新規顧客開拓業務を1日100件行うよう指示された営業職の事案。
〈裁判所の判断〉
新規顧客開拓のために訪問件数を目標として掲げること自体が不合理であるとは
いえないが、
・目標の達成のためには1件当たり数分で訪問しなければならないこと
・新卒社員が同業務を行う場合の件数は1日4、50件程度であること
・ポストインや門前払いが多くなければ達成できない件数の設定であること
から、当該目標は相当ハードルが高く、当該指示に合理的な理由があるとは認めら
れず、その他の事情をあわせて考慮した上で、当該指示は労働者に対する嫌がらせ
であり、不法行為を構成すると判断。慰謝料請求が認容された。
(大阪地裁 平成27年4月24日判決)